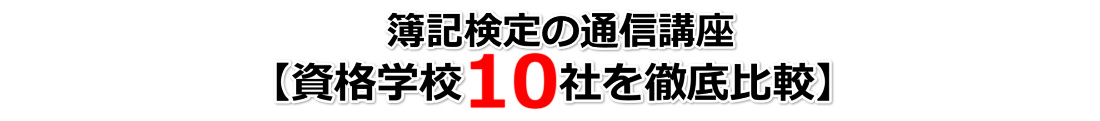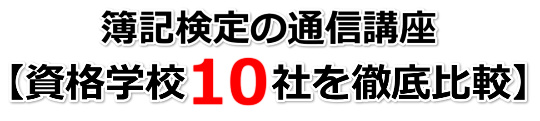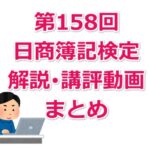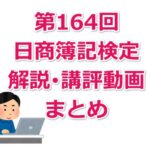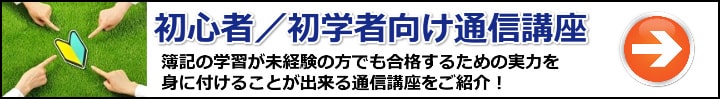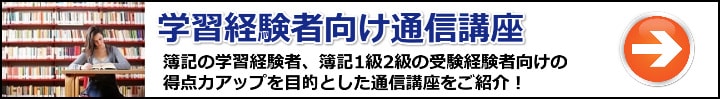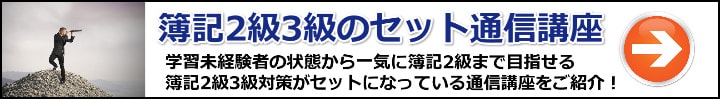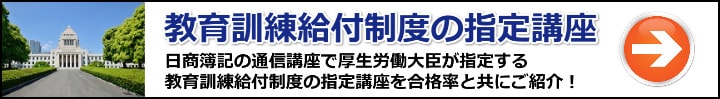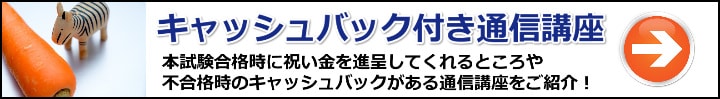日商簿記検定の合格率はどれくらい? 級ごとのデータを分析してみた
 これから日商簿記検定を受けようと考えておられる方にとって、合格率は非常に気になるところですよね。
これから日商簿記検定を受けようと考えておられる方にとって、合格率は非常に気になるところですよね。
これは日商簿記に限らず、どの資格試験でも「一体どれくらいの合格率なんだろう?」という疑問はほとんどの方が持つでしょう。
その出てきた過去の合格率によって、良くも悪くも気の持ちようが変わってしまいますからね(^^;
そこで今回は、日商簿記の初級と原価計算初級、3級〜1級までの合格率を洗い出し、級ごとに分析をしていきたいと思いますので一緒に見ていきましょう!
日商簿記初級・原価計算初級の合格率
まずは簿記の入門編である初級と原価計算初級の合格率から見てみましょう。
基本的に日商簿記の試験は2月・6月・11月の年3回行われ、1級のみ年に2回の施行となっておりましたが、この初級と原価計算初級に関しては近年新しくできた試験(※初級は2017年度、原価計算初級は2018年度より)で、年に何回試験が行われるか定めがありません。
これは、試験会場となる全国各地の「商工会議所ネット試験施行機関」がそれぞれ独自に試験日を決める形になっているためで、【第▲回の合格率は●●%!】という書き方ができないので、期間で区切ってご紹介します。
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2017年4月~2018年3月 | 4,167人 | 2,243人 | 53.83% |
| 2018年4月~2019年3月 | 4,182人 | 2,421人 | 57.89% |
| 2019年4月~2020年3月 | 4,284人 | 2,545人 | 59.41% |
| 平均合格率 | 57.04% | ||
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2018年4月~2019年3月 | 2,098人 | 1,954人 | 93.14% |
| 2019年4月~2020年3月 | 1,788人 | 1,641人 | 91.78% |
| 平均合格率 | 92.46% | ||
このデータを見てわかることといえば、とりあえず原価計算初級は超簡単!ということでしょうかw
色々な人が受験をする中で、合格率が90%以上もあるというのはかなり珍しい傾向です。
まだ試験が施行されるようになってから日が浅く、これから問題の見直しなどもあると思いますので、さすがにずっとこんな合格率ではないでしょうが、簿記の入門編というだけあってある程度合格率は高いままになるでしょうね。
試験の内容としては、簿記の基本的な用語や複式簿記・原価計算の仕組みを理解しているかどうかを問われる内容で、合格点はともに70点です。
ちなみに、初級に関しては2016年度までは「4級」という名目で行われていたので、一応そちらの過去10回分の合格率も見てみましょう。
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 136 | 437人 | 193人 | 44.16% |
| 137 | 603人 | 253人 | 41.96% |
| 138 | 428人 | 197人 | 46.03% |
| 139 | 404人 | 159人 | 39.36% |
| 140 | 559人 | 212人 | 37.92% |
| 141 | 478人 | 198人 | 41.42% |
| 142 | 418人 | 145人 | 34.69% |
| 143 | 627人 | 309人 | 49.28% |
| 144 | 429人 | 178人 | 41.49% |
| 145 | 527人 | 135人 | 25.62% |
| 平均合格率 | 40.19% | ||
こちらは期間で区切られていないので単純に比較はできませんが、まぁ難易度としては初級と同じくらいだと思っていただいていいかと思いますし、むしろ現時点では初級の方が合格率がいいので、受験する側からするとありがたいですよねw
日商簿記3級の合格率
続いて、3級の合格率です。ここからは主要な級になってきますので、第100回から現在までの合格率を見てみましょう。
簿記3級は「簿記資格を取りたい!」と思った時、多くの方がこの級から受験されます。
初級(4級)や原価計算初級が簿記の入門になるのですが、持っていてもあまり役に立たないのと知名度がないのとで、実質は3級が入門編と捉えていいと思います。
そのため、初級(4級)や原価計算初級に比べると受験者数がグンッと増えているのがお分かりいただけるかと思います。
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 100 | 70,143人 | 29,992人 | 42.76% |
| 101 | 77,664人 | 41,916人 | 53.97% |
| 102 | 85,612人 | 27,787人 | 32.46% |
| 103 | 72,508人 | 20,183人 | 27.84% |
| 104 | 84,309人 | 25,299人 | 30.01% |
| 105 | 90,469人 | 37,025人 | 40.93% |
| 106 | 72,277人 | 35,765人 | 49.48% |
| 107 | 79,163人 | 10,820人 | 13.67% |
| 108 | 94,581人 | 40,361人 | 42.67% |
| 109 | 70,262人 | 22,355人 | 31.82% |
| 110 | 79,825人 | 46,520人 | 58.28% |
| 111 | 89,482人 | 19,574人 | 21.87% |
| 112 | 80,570人 | 37,407人 | 46.43% |
| 113 | 78,640人 | 27,529人 | 35.01% |
| 114 | 93,890人 | 42,428人 | 45.19% |
| 115 | 74,059人 | 26,083人 | 35.22% |
| 116 | 85,872人 | 36,501人 | 42.51% |
| 117 | 95,925人 | 29,940人 | 31.21% |
| 118 | 83,112人 | 31,749人 | 38.20% |
| 119 | 91,522人 | 26,985人 | 29.48% |
| 120 | 103,333人 | 41,509人 | 40.17% |
| 121 | 93,453人 | 52,779人 | 56.48% |
| 122 | 107,000人 | 44,086人 | 41.20% |
| 123 | 108,429人 | 53,728人 | 49.55% |
| 124 | 95,092人 | 17,906人 | 18.83% |
| 125 | 113,269人 | 31,592人 | 27.89% |
| 126 | 117,180人 | 52,133人 | 44.49% |
| 127 | 91,077人 | 27,970人 | 30.71% |
| 128 | 93,091人 | 34,075人 | 36.60% |
| 129 | 105,106人 | 52,326人 | 49.78% |
| 130 | 80,887人 | 39,693人 | 49.07% |
| 131 | 83,409人 | 34,294人 | 41.12% |
| 132 | 95,847人 | 30,622人 | 31.95% |
| 133 | 84,846人 | 33,513人 | 39.50% |
| 134 | 85,585人 | 29,025人 | 33.91% |
| 135 | 93,781人 | 45,045人 | 48.03% |
| 136 | 75,049人 | 30,690人 | 40.89% |
| 137 | 78,726人 | 37,824人 | 48.05% |
| 138 | 86,659人 | 33,363人 | 38.50% |
| 139 | 79,460人 | 42,990人 | 54.10% |
| 140 | 79,467人 | 41,910人 | 52.74% |
| 141 | 84,708人 | 22,094人 | 26.08% |
| 142 | 89,012人 | 23,701人 | 26.63% |
| 143 | 83,915人 | 28,705人 | 34.21% |
| 144 | 94,411人 | 42,558人 | 45.08% |
| 145 | 80,832人 | 38,289人 | 47.37% |
| 146 | 80,227人 | 40,880人 | 50.96% |
| 147 | 88,970人 | 35,868人 | 40.31% |
| 148 | 78,243人 | 38,246人 | 48.88% |
| 149 | 79,421人 | 35,189人 | 44.31% |
| 150 | 88,774人 | 38,884人 | 43.80% |
| 151 | 80,360人 | 44,302人 | 55.13% |
| 152 | 72,435人 | 40,624人 | 56.08% |
| 153 | 80,130人 | 34,519人 | 43.08% |
| 154 | 76,896人 | 37,744人 | 49.08% |
| 155 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||
| 156 | 64,655人 | 30,654人 | 47.41% |
| 平均合格率 | 40.73% | ||
このように、日商簿記の中ではこの3級が1番受験者数が多く、1回あたりの受験者数がおよそ80,000人〜90,000人も受験しているわけです。
この数は、大体東京都世田谷区の方が皆いっせいに受けているのと同じような数字ですので、かなりの規模であることがわかるのではないでしょうか!(いまいちピンとこなかったらスイマセンw)
簿記資格は人気があるといいますが、この数字を見ると一目瞭然ですね。
で、合格率に関しては第100回から現在までの平均でも40%を越えていることからも、難易度は比較的易しいということがわかります。
受験している人のレベルも違うのでしょうが、4級の合格率と大して変わらないですからねw
合格点は初級と同じく70点がボーダーラインとなっています。
また、3級に関しては受験者の中に十分に勉強をせずに受験される方や学校や会社で強制的に受験させられた為、不真面目に受験される方も他の級に比べて多い傾向があるので、合格率も本来であればもう少し高いと想定してもいいかもしれませんね。
簿記のルールを学び、勘定科目や仕訳の理解をすることが出来れば決して難しくありませんし、合格するチャンスも多い級であるといえるでしょう。
日商簿記2級の合格率
お次は2級の第100回以降の合格率を見てみましょう。
合格点は70点と、初級や3級と変わらないのですが、2級からは試験科目に加わる【工業簿記】の存在が大きく、3級までは余裕で合格していたのに、2級から全くわからなくなったという方も非常に多いです。
何を隠そう、私もそのうちの一人ですw
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 100 | 46,689人 | 8,923人 | 19.11% |
| 101 | 46,842人 | 15,500人 | 33.09% |
| 102 | 59,213人 | 18,338人 | 30.97% |
| 103 | 49,777人 | 11,555人 | 23.21% |
| 104 | 48,785人 | 10,972人 | 22.49% |
| 105 | 58,852人 | 17,569人 | 29.85% |
| 106 | 49,051人 | 18,951人 | 38.64% |
| 107 | 43,540人 | 2,476人 | 5.69% |
| 108 | 59,904人 | 28,083人 | 46.88% |
| 109 | 42,928人 | 11,797人 | 27.48% |
| 110 | 39,859人 | 16,264人 | 40.80% |
| 111 | 55,876人 | 18,539人 | 33.18% |
| 112 | 48,273人 | 11,660人 | 24.15% |
| 113 | 45,293人 | 13,785人 | 30.44% |
| 114 | 59,212人 | 18,829人 | 31.80% |
| 115 | 52,104人 | 22,168人 | 42.55% |
| 116 | 44,242人 | 12,911人 | 29.18% |
| 117 | 60,887人 | 12,609人 | 20.71% |
| 118 | 57,812人 | 16,973人 | 29.36% |
| 119 | 50,573人 | 15,830人 | 31.30% |
| 120 | 61,662人 | 18,252人 | 29.60% |
| 121 | 60,475人 | 26,053人 | 43.08% |
| 122 | 57,616人 | 14,700人 | 25.51% |
| 123 | 74,371人 | 28,585人 | 38.44% |
| 124 | 66,330人 | 8,244人 | 12.43% |
| 125 | 67,337人 | 26,909人 | 39.96% |
| 126 | 69,100人 | 14,857人 | 21.50% |
| 127 | 66,838人 | 21,653人 | 32.40% |
| 128 | 52,546人 | 18,299人 | 34.82% |
| 129 | 64,052人 | 28,489人 | 44.48% |
| 130 | 53,404人 | 16,808人 | 31.47% |
| 131 | 48,341人 | 14,834人 | 30.69% |
| 132 | 61,796人 | 14,149人 | 22.90% |
| 133 | 57,898人 | 27,538人 | 47.56% |
| 134 | 42,703人 | 5,920人 | 13.86% |
| 135 | 60,377人 | 13,601人 | 22.53% |
| 136 | 55,960人 | 23,254人 | 41.55% |
| 137 | 40,330人 | 13,958人 | 34.61% |
| 138 | 54,188人 | 14,318人 | 26.42% |
| 139 | 55,225人 | 12,054人 | 21.83% |
| 140 | 47,480人 | 16,395人 | 34.53% |
| 141 | 59,801人 | 7,042人 | 11.78% |
| 142 | 70,402人 | 10,421人 | 14.80% |
| 143 | 44,364人 | 11,424人 | 25.75% |
| 144 | 56,530人 | 7,588人 | 13.42% |
| 145 | 60,238人 | 15,075人 | 25.03% |
| 146 | 43,767人 | 20,790人 | 47.50% |
| 147 | 47,917人 | 10,171人 | 21.23% |
| 148 | 48,533人 | 14,384人 | 29.64% |
| 149 | 38,352人 | 5,964人 | 15.55% |
| 150 | 49,516人 | 7,276人 | 14.69% |
| 151 | 49,776人 | 6,297人 | 12.65% |
| 152 | 41,995人 | 10,666人 | 25.40% |
| 153 | 48,744人 | 13,195人 | 27.07% |
| 154 | 46,939人 | 13,409人 | 28.57% |
| 155 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||
| 156 | 39,830人 | 7,255人 | 18.21% |
| 平均合格率 | 28.08% | ||
合格率が示している通り、2級になると難易度はかなり上がります。
過去の平均で見ると4人に1人くらいの割合でしか合格していないわけですので、私も合格した事を割と誇りに思っています!(←言い過ぎ)
2016年度より大幅な試験範囲の改定があり、それによってここ最近の合格率の変動幅は以前よりも大きくなっています。
それまでも2級は合格率の変動が激しかったのですが、第144回~147回あたりの合格率を見ていると、まるで全く違う試験を受けているかのような合格率の差になっています。
こういった試験範囲の改定があった時は、最後の追い込みをかける予想問題や過去問題だけでは対応できなくなるため、結果として合格率も下がってしまう傾向にあります。
しばらく試験範囲の改定はないかと思いますが、もし今後もあった場合は、試験範囲の改定をしてすぐの試験は避けたほうが無難かもしれません。
日商簿記1級の合格率
最後に1級の第100回以降の合格率を見てみましょう。
日商簿記1級は、取得すると税理士試験の受験資格を得ることができるため、難易度もかなり高くなっています。
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 101 | 13,672人 | 1,533人 | 11.21% |
| 102 | 17,614人 | 1,671人 | 9.49% |
| 104 | 14,801人 | 1,659人 | 11.21% |
| 105 | 17,937人 | 1,951人 | 10.88% |
| 107 | 14,481人 | 1,512人 | 10.44% |
| 108 | 16,705人 | 1,727人 | 10.34% |
| 110 | 13,703人 | 1,398人 | 10.20% |
| 111 | 16,609人 | 1,559人 | 9.39% |
| 113 | 12,838人 | 1,783人 | 13.89% |
| 114 | 15,338人 | 535人 | 3.49% |
| 116 | 13,345人 | 1,811人 | 13.57% |
| 117 | 15,913人 | 1,578人 | 9.92% |
| 119 | 13,043人 | 1,105人 | 8.47% |
| 120 | 15,889人 | 1,479人 | 9.31% |
| 122 | 14,399人 | 1,464人 | 10.17% |
| 123 | 16,568人 | 1,518人 | 9.16% |
| 125 | 15,367人 | 1,338人 | 8.71% |
| 126 | 17,027人 | 2,258人 | 13.26% |
| 128 | 13,160人 | 1,365人 | 10.37% |
| 129 | 14,731人 | 1,919人 | 13.03% |
| 131 | 11,960人 | 1,455人 | 12.17% |
| 132 | 13,146人 | 1,690人 | 12.86% |
| 134 | 10,143人 | 984人 | 9.70% |
| 135 | 11,037人 | 1,153人 | 10.45% |
| 137 | 8,738人 | 847人 | 9.69% |
| 138 | 9,931人 | 877人 | 8.83% |
| 140 | 8,108人 | 716人 | 8.83% |
| 141 | 9,087人 | 873人 | 9.61% |
| 143 | 7,792人 | 846人 | 10.86% |
| 144 | 8,416人 | 783人 | 9.30% |
| 146 | 7,103人 | 626人 | 8.81% |
| 147 | 8,286人 | 487人 | 5.88% |
| 149 | 7,501人 | 1,007人 | 13.42% |
| 150 | 7,588人 | 680人 | 8.96% |
| 152 | 6,788人 | 575人 | 8.47% |
| 153 | 7,520人 | 735人 | 9.77% |
| 155 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||
| 156 | 8,553人 | 1,158人 | 13.54% |
| 平均合格率 | 10.21% | ||
この表の合格率を見てみても、合格率が10%を切っている回が多数あり、最高合格率も13%程度であることからも、生半可な気持ちでは受からない試験であることがわかります。
酷いときは合格率が3%程度だったこともあるくらいですので、行政書士や宅建士といった国家資格の試験とも変わらないような難易度であるともいえます。
1級の合格点としては他の級と同じく70点となりますが、商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目(配点は各25点)のうち、1科目でも10点未満を取ってしまうと、合計で70点以上取得できても不合格となってしまう「足切り制度」という特徴があるため、これも合格率を下げている要因のひとつであると考えられます。
やはり簿記1級の資格を取得するとなると独学ではかなり難しい試験となっていますので、資格学校や通信講座をきちんと受講して目指すのが最短の道だと言えるでしょう。
なお、1級の試験は6月と11月の年2回で、他の級のように年3回実施されませんのでご注意下さい。
日商簿記検定級ごとの合格率まとめ

ここまで日商簿記の合格率を級ごとに見てきましたが、トータルして言える事は「しっかり勉強をしていけば、難しすぎて取得できない!というような資格ではない」ということです。
1級ともなると合格率も毎回10%前後という低い数字になりますので、誰でも簡単に受かるというものではありませんし、努力は必要です。
ただ、努力したらした分だけ報われるのが簿記資格の検定試験で、いかに真面目にコツコツ勉強をできるかがポイントになってきます。
本当に地味ですが、テキストを何度も読み返し問題集を繰り返し解くことで、例え1級であっても合格できる可能性はかなり高くなります。
逆に、合格率を見て「余裕でしょ!」などと油断して少しでも勉強をサボってしまうと、どの級を受けるにしても細かな部分でミスをして合格できないという事も往々にしてあり得ますので、油断は禁物です。
日商の簿記試験は全て「絶対評価」で合格点が決まっており、「1点でも多く点数を取る!」という心構えが合格への近道になってくると思いますので、学習するときから常にその部分を意識して取り組むようにして下さいね!