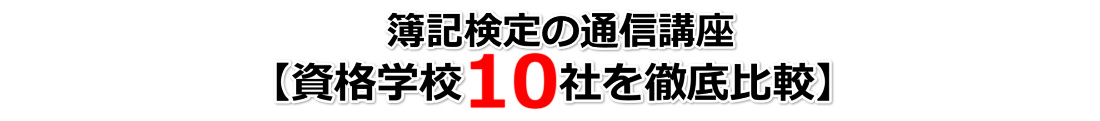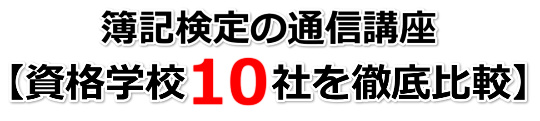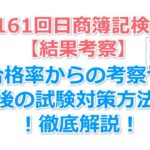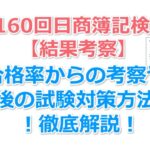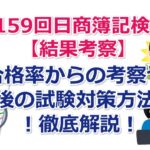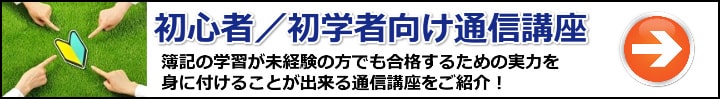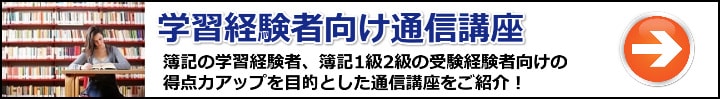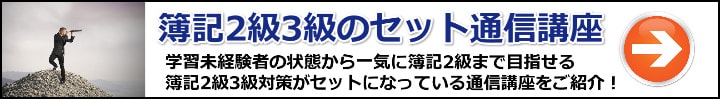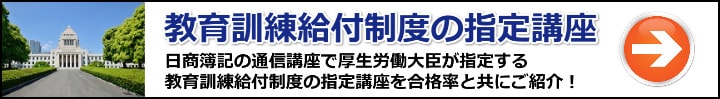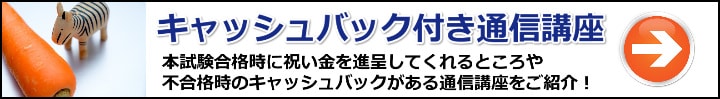簿記資格の種類と違い〜日商/全商/全経の級ごとの難易度・合格率を比較〜
 『簿記資格』とひとくくりにいっても、主催している団体も試験の内容も違う複数の簿記資格があるということをご存知でしょうか?
『簿記資格』とひとくくりにいっても、主催している団体も試験の内容も違う複数の簿記資格があるということをご存知でしょうか?
簿記資格の種類は有名なところで言うと「日商簿記」「全商簿記」「全経簿記」というものがあります。
なぜこのように種類があるのかというと、簿記資格が国の法律に基づいて定められた国家資格ではなく、都道府県や市区町村の条例に基づいて定められた公的資格になるからで、それぞれ各団体が主催しているので複数の簿記資格があるというわけです。
これらは主催しているところが違うというのはもちろんですが、難易度もそれぞれかなり差がありますので、できるだけわかりやすいように解説していきます!
①難易度…★☆☆ 全商簿記の学習内容や合格率
まずはこの3つの中で難易度が一番低い全商簿記から解説します。
全商簿記というのは、正式名称は「全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定」という資格で、公益財団法人全国商業高等学校協会が主催している資格になります。
この主催しているところを聞いて想像できるかと思いますが、主に受験者は商業高校の生徒ということになります。
試験の内容としては学校教育で学べることが中心のため、他の簿記資格に比べると難易度は低めとなっています。
級は3級、2級、1級とあり、1級に関しては「会計」と「原価計算」に分かれています。
受験料と主な学習内容は以下の通りです。
| 級 | 受験料 | 学習内容等 |
| 3級 | 1,300円 | 商品売買業を営む個人企業の基礎・基本となる会計処理を学ぶ。 |
| 2級 | 1,300円 | 商品売買業を営む個人企業の発展的な会計処理と、株式会社の基本的な会計処理について学ぶ。 |
| 1級 会計 |
1,300円 | 株式会社の会計処理を中心に会計法規や企業の業績測定等に関する内容を学ぶ。 |
| 1級 原価計算 |
1,300円 | 製造業で用いられる簿記で、製品の製造に要した金額(原価)の計算手続きについて学ぶ。 |
受験料に関しては、どの級を受験するにも一律1,300円という安価で受験することができます。
また、直近10回の合格率も表でまとめてみました。試験は毎年1月・6月の第4日曜日の2回行われます。
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 80 | 12,925人 | 5,723人 | 44.28% |
| 81 | 38,179人 | 23,966人 | 62.77% |
| 82 | 11,640人 | 5,268人 | 45.26% |
| 83 | 38,425人 | 23,659人 | 61.57% |
| 84 | 11,438人 | 4,862人 | 42.51% |
| 85 | 38,133人 | 24,237人 | 63.56% |
| 86 | 10,317人 | 5,283人 | 51.21% |
| 87 | 35,696人 | 22,556人 | 63.19% |
| 88 | 9,010人 | 3,931人 | 43.63% |
| 89 | 35,403人 | 24,070人 | 67.99% |
| 平均合格率 | 54.60% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 80 | 15,340人 | 6,390人 | 41.66% |
| 81 | 47,041人 | 28,545人 | 60.68% |
| 82 | 15,501人 | 5,979人 | 38.57% |
| 83 | 48,163人 | 30,107人 | 62.51% |
| 84 | 15,734人 | 5,504人 | 34.98% |
| 85 | 48,838人 | 34,255人 | 70.14% |
| 86 | 13,886人 | 5,564人 | 40.07% |
| 87 | 46,499人 | 20,764人 | 44.65% |
| 88 | 17,199人 | 6,707人 | 39.00% |
| 89 | 44,531人 | 21,473人 | 48.22% |
| 平均合格率 | 48.05% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 80 | 16,783人 | 6,804人 | 40.54% |
| 81 | 36,209人 | 17,494人 | 48.31% |
| 82 | 17,294人 | 4,102人 | 23.72% |
| 83 | 37,916人 | 10,477人 | 27.63% |
| 84 | 21,292人 | 12,367人 | 58.08% |
| 85 | 34,251人 | 13,080人 | 38.19% |
| 86 | 17,830人 | 2,266人 | 12.71% |
| 87 | 37,014人 | 15,524人 | 41.94% |
| 88 | 15,447人 | 5,652人 | 36.59% |
| 89 | 33,484人 | 12,772人 | 38.14% |
| 平均合格率 | 36.59% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 80 | 25,292人 | 10,412人 | 41.17% |
| 81 | 33,066人 | 16,411人 | 49.63% |
| 82 | 23,931人 | 11,310人 | 47.26% |
| 83 | 33,015人 | 15,393人 | 46.62% |
| 84 | 23,551人 | 11,324人 | 48.08% |
| 85 | 31,443人 | 13,994人 | 44.51% |
| 86 | 23,443人 | 8,553人 | 36.48% |
| 87 | 32,172人 | 14,875人 | 46.24% |
| 88 | 22,351人 | 9,423人 | 42.16% |
| 89 | 30,694人 | 14,253人 | 46.44% |
| 平均合格率 | 44.86% | ||
合格率は3級と2級は約50%と、受験者の約半数が合格するという非常に難易度が易しい試験です。
ただ、さすがに1級になると合格率は一気に10%ほど下がり、会計・原価計算ともに40%前後という数字になります。
それでも、1級でおよそ40%の合格率があるということを踏まえても、かなり易しい資格であるという事がお分かりいただけるかと思います。
このように合格率が軒並み高いのは、全商簿記は全国の商業高校の生徒が対象のため、位置づけが「落とす試験」ではなく「合格させる試験」だからだと言われています。
②難易度…★★☆ 全経簿記の学習内容や合格率
次に、全商簿記より少し難易度が上がる全経簿記を解説します。
全経簿記は、「公益社団法人全国経理教育協会主催 簿記能力検定試験」の略で、文部科学省の認定を受けている資格です。
先ほどの全商簿記は全国の商業高校に通う高校生が対象でしたが、全経簿記は専門学校生が主な対象者となってきます。
とはいえ、専門学校生のみならず、仕事で経理業務などをされる方のスキルアップとして受験される方も多くいらっしゃいます。
全経簿記は基礎簿記会計、3級、2級、1級、上級とあり、2級は「商業簿記」と「工業簿記」、1級は「商業簿記・会計学」と「原価計算・工業簿記」に分かれています。
各級の受験料と学習内容をまとめました。
| 級 | 受験料 | 学習内容等 |
| 基礎簿記 会計 |
1,200円 | 商品売買業を営む個人企業の基礎・基本となる会計処理を学ぶ。 |
| 3級 | 1,400円 | 商品売買業を営む個人企業の会計処理と、小規模株式会社の基本的な会計処理について学ぶ。 |
| 2級 商業簿記 |
1,700円 | 商品売買業を営む個人企業の発展的な会計処理と、中規模株式会社の基本的な会計処理について学ぶ。 |
| 2級 工業簿記 |
1,700円 | 製造業で用いられる工業簿記の基礎を学ぶ。 |
| 1級 商業簿記 会計学 |
2,200円 | 大規模株式会社の会計処理を中心に会計法規や企業の業績測定等に関する内容を学ぶ。 |
| 1級 原価計算 工業簿記 |
2,200円 | 製造業で用いられる工業簿記の発展的な処理方法や計算方法を学ぶ。 |
| 上級 | 7,500円 | 商業簿記、会計学、工業簿記及び原価計算について高度な知識を学び、併せて複雑な実務処理能力を習得する。 |
受験料は基礎簿記会計から1級までは1,200円〜2,200円と比較的受験しやすい金額ですが、上級になると7,500円の受験料がかかります。
まぁ、全経簿記の上級を取得すると税理士試験の受験資格を貰えるくらいのモノなので、これくらいの金額は当たり前かもしれませんね。
お次に、直近10回の合格率を表にまとめてみました。試験は毎年2月・5月・7月・11月の4回行われます。(上級のみ年2回)
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 188 | 1,513人 | 1,041人 | 68.80% |
| 189 | 966人 | 626人 | 64.80% |
| 190 | 119人 | 88人 | 73.95% |
| 191 | 992人 | 770人 | 77.62% |
| 192 | 1,288人 | 973人 | 75.54% |
| 193 | 887人 | 662人 | 74.63% |
| 194 | 59人 | 49人 | 83.05% |
| 195 | 1,041人 | 766人 | 73.58% |
| 196 | 1,353人 | 1,098人 | 81.15% |
| 197 | 880人 | 557人 | 63.30% |
| 平均合格率 | 73.64% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 188 | 8,573人 | 6,373人 | 74.34% |
| 189 | 8,107人 | 3,657人 | 45.11% |
| 190 | 1,604人 | 955人 | 59.54% |
| 191 | 5,989人 | 3,600人 | 60.11% |
| 192 | 8,567人 | 5,470人 | 63.85% |
| 193 | 8,321人 | 3,720人 | 44.71% |
| 194 | 1,897人 | 1,232人 | 64.94% |
| 195 | 5,451人 | 2,973人 | 54.54% |
| 196 | 8,370人 | 5,644人 | 67.43% |
| 197 | 7,678人 | 5,059人 | 65.89% |
| 平均合格率 | 60.05% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 188 | 3,035人 | 959人 | 31.60% |
| 189 | 4,069人 | 1,327人 | 32.61% |
| 190 | 1,069人 | 662人 | 61.93% |
| 191 | 1,816人 | 890人 | 49.01% |
| 192 | 2,629人 | 824人 | 31.34% |
| 193 | 3,849人 | 1,741人 | 45.23% |
| 194 | 989人 | 454人 | 45.90% |
| 195 | 2,130人 | 1,119人 | 52.54% |
| 196 | 2,147人 | 1,185人 | 55.19% |
| 197 | 3,021人 | 1,466人 | 48.53% |
| 平均合格率 | 45.39% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 188 | 502人 | 398人 | 79.28% |
| 189 | 575人 | 498人 | 86.61% |
| 190 | 220人 | 183人 | 83.18% |
| 191 | 582人 | 442人 | 75.95% |
| 192 | 859人 | 627人 | 72.99% |
| 193 | 593人 | 438人 | 73.86% |
| 194 | 341人 | 202人 | 59.24% |
| 195 | 895人 | 728人 | 81.34% |
| 196 | 1,109人 | 670人 | 60.41% |
| 197 | 740人 | 396人 | 53.51% |
| 平均合格率 | 72.64% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 188 | 687人 | 269人 | 39.16% |
| 189 | 587人 | 129人 | 21.98% |
| 190 | 474人 | 245人 | 51.69% |
| 191 | 640人 | 149人 | 23.28% |
| 192 | 573人 | 267人 | 46.60% |
| 193 | 499人 | 216人 | 43.29% |
| 194 | 447人 | 245人 | 54.81% |
| 195 | 639人 | 141人 | 22.07% |
| 196 | 647人 | 369人 | 57.03% |
| 197 | 505人 | 157人 | 31.09% |
| 平均合格率 | 39.10% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 188 | 781人 | 395人 | 50.58% |
| 189 | 783人 | 509人 | 65.01% |
| 190 | 291人 | 157人 | 53.95% |
| 191 | 595人 | 316人 | 53.11% |
| 192 | 534人 | 305人 | 57.12% |
| 193 | 593人 | 342人 | 57.67% |
| 194 | 495人 | 271人 | 54.75% |
| 195 | 742人 | 514人 | 69.27% |
| 196 | 614人 | 340人 | 55.37% |
| 197 | 652人 | 412人 | 63.19% |
| 平均合格率 | 58.00% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 181 | 2,482人 | 446人 | 17.97% |
| 183 | 2,133人 | 379人 | 17.77% |
| 185 | 2,220人 | 417人 | 18.78% |
| 187 | 1,920人 | 305人 | 15.89% |
| 189 | 2,210人 | 335人 | 15.16% |
| 191 | 1,935人 | 321人 | 16.59% |
| 193 | 2,171人 | 351人 | 16.17% |
| 195 | 1,929人 | 314人 | 16.28% |
| 197 | 2,082人 | 318人 | 15.27% |
| 199 | 1,545人 | 238人 | 15.40% |
| 平均合格率 | 16.53% | ||
こちらの表を見てみると、1級でも合格率が非常に高いのがわかりますし、特に原価計算・工業簿記の方は毎回50%超えとかなり高確率で合格できる試験ということがわかります。
ただ、さすがに上級ともなると合格率は20%弱で推移しており、生半可な勉強では受からないことは数字が示しています。
合格率を見ても分かるように、1級までは比較的合格率が高くなっていますので、自分の知識やスキルに自信をつけるにはもってこいの資格といえます。
どんな資格でも【1級】を持ってると何か気持ちいいですよね!(私だけ?笑)
また、先ほども書きましたが、この全経簿記の上級を取得すると税理士試験の受験資格を得る事ができるというメリットもありますので、ステップアップを目指す方は是非受けてみましょう!
③難易度…★★★ 日商簿記の学習内容や合格率
「簿記」と聞くと多くの方が連想するのがこの「日商簿記」です。
日商簿記は日本商工会議所が主催しており、知名度が高く受験者数も多い簿記資格です。
こちらも文部科学省の認定を受けている資格となり、歴史はかなり古く1954年から始まりました。
級は初級、原価計算初級、3級、2級、1級とあるのですが、正直、初級と原価計算初級に関しては簿記の超入門編といったところなので、持っていたところでそんなに役に立たないのが現状です^^;
あとでこの2つ(特に原価計算初級)の合格率を見たら驚愕すると思いますw
実際に就職活動で役に立ってくるのは3級よりも上の級になり、会計や経理、財務を望む方は2級を持っていると結構な強みになります。
管理人も日商簿記2級に合格し、経理職に転職した経験があります!
では、各級の受験料と学習内容を見てみましょう。
| 級 | 受験料 | 学習内容等 |
| 初級 | 2,200円 | 簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを学ぶ。 |
| 原価計算 初級 |
2,200円 | 原価計算の基本用語や、原価と利益の関係を学ぶ。 |
| 3級 | 2,850円 | 商品売買業を営む個人企業の発展的な会計処理と、株式会社の基本的な会計処理について学ぶ。 |
| 2級 | 4,720円 | 株式会社の高度な会計処理と、製造業で用いられる工業簿記の基礎を学ぶ。 |
| 1級 | 7,850円 | 極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算・会計基準や会社法などの企業会計に関する法規を学び、経営管理や経営分析ができるようになる。 |
このように、受験料は全商簿記や全経簿記と比べるといくらか高めの設定となっています。
で、難易度が一番高いとされる日商簿記ですが、試験は年に3回(2月・6月・11月)行われ、1級は年に2回の施行になります。
直近の合格率は以下のようになっています。
(※初級は2017年度、原価計算初級は2018年度からできた新しい試験で、インターネットを介した試験方式なので、期間で合格率を算出しています)
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2017年4月~2018年3月 | 4,167人 | 2,243人 | 53.83% |
| 2018年4月~2019年3月 | 4,182人 | 2,421人 | 57.89% |
| 2019年4月~2020年3月 | 4,284人 | 2,545人 | 59.41% |
| 平均合格率 | 57.04% | ||
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2018年4月~2019年3月 | 2,098人 | 1,954人 | 93.14% |
| 2019年4月~2020年3月 | 1,788人 | 1,641人 | 91.78% |
| 平均合格率 | 92.46% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 145 | 80,832人 | 38,289人 | 47.37% |
| 146 | 80,227人 | 40,880人 | 50.96% |
| 147 | 88,970人 | 35,868人 | 40.31% |
| 148 | 78,243人 | 38,246人 | 48.88% |
| 149 | 79,421人 | 35,189人 | 44.31% |
| 150 | 88,774人 | 38,884人 | 43.80% |
| 151 | 80,360人 | 44,302人 | 55.13% |
| 152 | 72,435人 | 40,624人 | 56.08% |
| 153 | 80,130人 | 34,519人 | 43.08% |
| 154 | 76,896人 | 37,744人 | 49.08% |
| 155 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||
| 平均合格率 | 48.90% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 145 | 60,238人 | 15,075人 | 25.03% |
| 146 | 43,767人 | 20,790人 | 47.50% |
| 147 | 47,917人 | 10,171人 | 21.23% |
| 148 | 48,533人 | 14,384人 | 29.64% |
| 149 | 38,352人 | 5,964人 | 15.55% |
| 150 | 49,516人 | 7,276人 | 14.69% |
| 151 | 49,776人 | 6,297人 | 12.65% |
| 152 | 41,995人 | 10,666人 | 25.40% |
| 153 | 48,744人 | 13,195人 | 27.07% |
| 154 | 46,939人 | 13,409人 | 28.57% |
| 155 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||
| 平均合格率 | 24.73% | ||
| 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 140 | 8,108人 | 716人 | 8.83% |
| 141 | 9,087人 | 873人 | 9.61% |
| 143 | 7,792人 | 846人 | 10.86% |
| 144 | 8,416人 | 783人 | 9.30% |
| 146 | 7,103人 | 626人 | 8.81% |
| 147 | 8,286人 | 487人 | 5.88% |
| 149 | 7,501人 | 1,007人 | 13.42% |
| 150 | 7,588人 | 680人 | 8.96% |
| 152 | 6,788人 | 575人 | 8.47% |
| 153 | 7,520人 | 735人 | 9.77% |
| 155 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||
| 平均合格率 | 9.39% | ||
上の表でわかるように、全商簿記や全経簿記に比べても合格率はかなり落ちます。
1級に至っては直近10回の試験で合格率の平均が10%を割っていることからも、その難易度の高さが伺えますね。
なお、全経簿記上級と同じく、日商簿記1級の合格者にも税理士試験の受験資格が与えられるのですが、全経上級の平均合格率が20%弱あるのに対し、日商簿記1級の平均合格率は10%程度と、約2倍の差があります。
この事実からも、税理士試験の受験資格のことだけを考えれば、日商簿記1級よりも合格の可能性が高い全経簿記上級の合格を目指したほうが賢いかもしれません。
各簿記資格の違いと難易度まとめ

ここまで「日商簿記」「全商簿記」「全経簿記」の違いや難易度比較をしてきましたが、相対して見てみると日商簿記1級だけが飛び抜けて難易度が高く、次いで全経簿記上級、日商簿記2級、全経簿記1級、全商簿記1級…という試験の難易度になるかと思います。
ここでひとつ言いたいのですが、全商簿記1級や全経簿記1級を持っている方はぜひ、日商簿記2級にもチャレンジしてみてください!
試験の難易度としては日商簿記2級の方が高いですが、全商や全経の1級を持っている方は簿記知識の基盤は間違いなく持っておられますし、そうなると日商簿記2級の合格もかなり見えてきていると思います。
日商簿記は知名度も高く企業が求める人材としている場合が多いので、日商簿記2級を持っていれば大体の企業から一目置かれます。
逆に日商簿記3級までだと履歴書に書いてもそこまで目にとまりませんし、仮に全商簿記1級や全経簿記1級を持っていたとしても、就職活動などで思っているような評価が得られない可能性があります。
せっかく日商簿記2級と同等の知識があっても周囲に伝わらなくては損をすることしかないので、是非チャレンジしてみて下さいね!